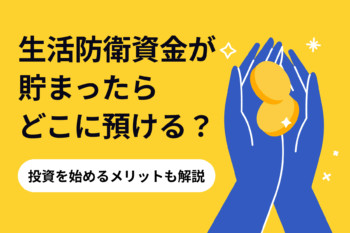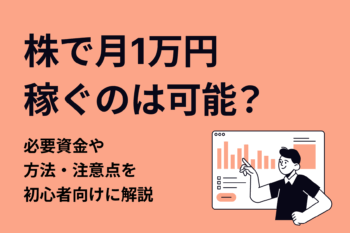近年、銀行預金金利は上昇傾向にありますが、それでも1%を超えることはほとんどありません。 また、著しい物価上昇が続くなかで、現金しか保有していない人の資産は実質的に目減りしていきます。 そのため、資産を守りつつ将来に備え […]
近年、銀行預金金利は上昇傾向にありますが、それでも1%を超えることはほとんどありません。
また、著しい物価上昇が続くなかで、現金しか保有していない人の資産は実質的に目減りしていきます。
そのため、資産を守りつつ将来に備えるには、投資に取り組むことが必要不可欠です。
しかし、投資に対して高いハードルを感じている人や、仕事が忙しくて投資に費やす時間を作れない人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、初心者の方でも簡単にできる投資手法を紹介します。
投資を成功させるためのコツや投資の始め方なども詳しくまとめているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。
- 簡単にできる投資手法は?
⇒ 不動産クラウドファンディングや投資信託がおすすめ! - 初心者には難しい投資手法は?
⇒ FXや仮想通貨投資などはハイリスクなので要注意! - 投資を始める際に押さえておくべきポイントは?
⇒ できるだけリスクを抑えた運用を意識することが重要!
目次
- 簡単にできる投資手法かどうかを判断する際のポイント
- ほったらかしで運用できるか
- リスクは高くないか
- 少額で始められるか
- 簡単にできる投資手法7選
- 不動産クラウドファンディング
- 投資信託
- ETF(上場投資信託)
- REIT(不動産投資信託)
- 個人向け国債
- 金投資
- 単元未満株投資
- 初心者にとって簡単とはいえない投資手法は?
- 投資で稼ぐのは簡単?資金別の運用シミュレーション
- 初心者が押さえておくべき投資の基本
- リターンを求めすぎない
- 「長期・積立・分散」を意識する
- 利益は積極的に再投資する
- 投資アプリで勉強しておく
- ポートフォリオを定期的に更新する
- ロボアドバイザーの利用を検討する
- 公的制度を活用する
- NISA(少額投資非課税制度)
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
- 投資を始めるのは簡単!基本的な4つのステップ
- 余剰資金を洗い出す
- 運用目的・リスク許容度を明確にする
- 投資に関する基本的な知識を学ぶ
- 資金量やライフスタイルに合った投資手法を実践する
- まとめ
簡単にできる投資手法かどうかを判断する際のポイント
投資手法は数多く存在し、それぞれ難易度にも違いがあります。
そのなかで、簡単にできる投資手法かどうかを判断する際には、以下のポイントに着目しておくとよいでしょう。
- ほったらかしで運用できるか
- リスクは高くないか
- 少額で始められるか
具体的にどのような投資手法が該当するのかも含めて、それぞれのポイントを詳しくみていきましょう。
ほったらかしで運用できるか
投資手法の選択において「ほったらかしで運用できるか」は重要な判断基準です。
自動化された仕組みで運用益を得ることができれば、投資に時間をかけられない人でも無理なく続けられます。
また、ほったらかしで運用ができる投資手法であれば、相場の変動に惑わされることなく、感情的な売買を防げる点もメリットのひとつです。
特に投資経験が浅いうちは、価格下落時のパニック売りなどで大きな損失を出してしまうケースも多く、事前設定に従って機械的に処理が進められる「ほったらかし運用」のほうが利益を出しやすい傾向があります。
たとえば、投資信託は保有しているだけで定期的に分配金が付与されるので、ほったらかし運用の代表例といえるでしょう。
とはいえ、ほったらかしで運用できる投資手法でも、投資対象や資産配分の定期的な見直しは必要です。
「完全放置」ではなく「最小限の手間で最大効果を得る」という意識を持つようにしてください。
リスクは高くないか
簡単にできる投資手法を探しているのであれば、リスクが高くないかを最低限確認しておくべきです。
投資の世界において、リターンとリスクは比例関係にあります。
ハイリスクな投資手法を選ぶと、大きな利益を得られる可能性がある反面、取り返しのつかない損失を招く可能性もゼロではありません。
たとえば、FXでは自己資金の25倍もの資金を動かして取引できるため、少額でもハイリターンを狙えますが、予想が外れたときの損失も大きく、一晩で資産を失ってしまうことすらあり得るのです。
ただし、リスクを廃除しすぎると、ほとんどリターンを得られないまま終わってしまう可能性もあります。
あくまでも、自身のライフプランや資産状況に応じたリスク水準を見極め、それに見合った投資手法を選ぶことが大切です。
少額で始められるか
少額で始められることも、投資手法の難易度が低いことを表す要素のひとつです。
投資には損失のリスクがつきものですが、そもそもの投資額が小さければ、損失のダメージも最小限に抑えられます。
そのため、心理的・金銭的な負担を軽減しながら投資経験を積むことができるのです。
たとえば、100円から購入できる投資信託や1万円程度で出資できる不動産クラウドファンディングなどが少額投資に適した手法といえます。
とはいえ、少額投資を続けていても資産は思うように増えないので、投資の知識・経験が身に付いた段階で、徐々に投資金額を追加していくことも重要です。
簡単にできる投資手法7選
簡単にできる投資手法としては、以下の7つが挙げられます。
- 不動産クラウドファンディング
- 投資信託
- ETF(上場投資信託)
- REIT(不動産投資信託)
- 個人向け国債
- 金投資
- 単元未満株投資
それぞれの仕組みやメリット・デメリットを解説します。
不動産クラウドファンディング
不動産クラウドファンディングとは、不特定多数の投資家からオンライン上で集めた資金を元手に、事業者が不動産を購入・運用する仕組みのことです。
投資家は気に入ったファンドに出資するだけで運用益の一部を受け取れるので、初心者でも手軽に始められる投資手法として注目されています。
また、多くのクラウドファンディングサービスでは最低出資額を1万円程度に設定しており、不動産関連の投資を少額で始められることも魅力のひとつといえるでしょう。
不動産クラウドファンディングのメリット・デメリットは以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
| ・少額投資が可能・価格変動による損失のリスクがない・投資家の元本が守られる仕組みがある・不動産運用をプロに任せられる | ・原則として中途解約は認められない・人気ファンドへの出資は競争が激しい |
なお、多くの不動産クラウドファンディングでは「優先劣後方式」が採用されています。
仮に損失が生じたときも事業者の出資分から優先的に補填されるため、投資家の元本割れリスクが抑えられているのです。
少しでも不動産クラウドファンディングに興味がある方は、不動産BANKの公式サイトをチェックしてみてください。
不動産BANKでは収益が出やすい首都圏の中古物件を取り扱っており、安定して高利回りを実現しています。
随時、新たなファンドが立ち上がっているので、いつでも出資できるように会員登録だけでも済ませてみてはいかがでしょうか。
投資信託
投資信託は、投資家から集めた資金をもとに、事業者が株式や債券などを運用する金融商品です。
投資家には投資信託の保有量に応じて、定期的に分配金が付与されます。
プロが運用を代行してくれるうえ、証券会社によっては100円からでも投資できるので、初心者の方には特に適した投資手法といえるでしょう。
また、投資信託はひとつの銘柄が複数の投資対象で構成されているため、自動的に分散投資ができる点も特徴的です。
投資信託のメリット・デメリットとしては、以下の点が挙げられます。
| メリット | デメリット |
| ・手軽に分散投資ができる・少額で始められる・運用をプロに任せられる | ・信託報酬が発生する・注文時と約定時の取引価格が乖離することがある |
投資信託は新NISAの対象になっていることもあり、人気の高い金融商品です。
ただし、投資信託を保有している限り、手数料として年率0.5%~2.5%程度の信託報酬を支払い続ける必要がある点に注意しておきましょう。
投資信託は長期保有を前提としており、信託報酬が数%違うだけでも資産の増え幅が大きく変わってくるので、できるだけ年率が低いものを選ぶようにしてください。
ETF(上場投資信託)
ETF(上場投資信託)は、証券取引所に上場している投資信託のことです。
通常の投資信託は注文と約定のタイミングにラグが生じますが、ETFは株式のようにリアルタイムで売買できる点が大きな違いといえるでしょう。
とはいえ、投資家が出資し、事業者が運用するという仕組みは変わらないので、投資家側はほとんど手間をかけずに運用益の一部を得ることができます。
ETFのメリット・デメリットとしては、次の点が挙げられます。
| メリット | デメリット |
| ・証券取引所を介したリアルタイムの取引が可能・保有コストが抑えられている | ・分配金の自動再投資機能がない・売買できる銘柄数が少ない |
多くのETFは日経平均株価やTOPIXなどの特定の指標に連動するように運用されているため、初心者でも値動きが分かりやすいです。
また、通常の投資信託と比較して保有コストが低い点もETFの特徴といえます。
REIT(不動産投資信託)
REIT(不動産投資信託)は、投資家から集めた資金を元手に、事業者が不動産を運用する金融商品です。
現物不動産投資では多額の初期費用が必要ですが、REITであれば数万円程度で不動産への投資を始められます。
REITのメリット・デメリットは、次のとおりです。
| メリット | デメリット |
| ・利回りが高くなりやすい・少額で不動産に投資できる | ・金利変動の影響を受ける・現物不動産の所有権を得られるわけではない |
REITには、利益の9割超を還元した事業者が税制優遇を受けられる仕組みがあります。
そのため、利益が分配金に回されやすくなり、高い利回りが期待できるのです。
ただし、投資対象となるのはあくまでもファンドであり、現物不動産を所有できるわけではないので節税効果には期待できません。
個人向け国債
個人向け国債は、国が資金調達のために発行する債券を購入し、利子を受け取る投資手法のことです。
満期まで保有していれば投資額が全額戻ってくるので、利子の分だけほぼ確実に利益を出すことができます。
購入後1年経過すれば中途換金も可能で、受け取れる利子は少なくなりますが、それでも元本割れすることは基本的にありません。
個人向け国債のメリットとデメリットは、次のとおりです。
| メリット | デメリット |
| 元本割れのリスクがほぼない少額で購入できる最低金利の保証がある | リターンが小さい購入後1年間は換金できないインフレに弱い |
個人向け国債には、固定金利型の満期3年・5年タイプ、変動金利型の満期10年タイプがあります。
それぞれ満期や金利に違いがあるので、自身の運用方針に適したものを選択してください。
| 固定3年 | 固定5年 | 変動10年 | |
| 満期 | 3年 | 5年 | 10年 |
| 金利タイプ | 固定金利 | 変動金利 | |
| 適用金利 | 基準金利-0.03% | 基準金利-0.05% | 基準金利×0.66 |
| 金利の下限 | 0.05% | ||
| 最低購入価格 | 1万円 | ||
| 中途換金時の利子 | 直前2回分の各利子相当額×0.79685が差し引かれる | ||
たとえば「固定5年」を選べば、結婚資金や教育資金の準備など中期的な目標にあわせた運用が可能です。
一方「変動10年」は、長期で金利上昇を見込む場合に有効な選択肢といえるでしょう。
近年は金利も上昇傾向にあり、発行のタイミング次第では1%近い利回りで運用することもできます。
金投資
金投資は、金を対象にして資産運用をおこなう手法のことです。
安いときに買って高いときに売れば利益を出すことができますが、短期的な取引ではなく、安全資産として長期的に保有するケースが一般的といえるでしょう。
金投資のメリット・デメリットは以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
| 無価値にならないインフレに強い換金性が高い | 現物の金投資は保有コストがかかる不労所得にはつながらない |
金に投資する際は現物を保有するのもひとつですが、金の値動きに連動する投資信託やETFに出資するのもよいでしょう。
また、積立で購入すれば取引価格が平準化されるので、高値掴みのリスクを抑えられます。
単元未満株投資
単元未満株投資は、1~99株単位で株式を購入する投資手法のことです。
通常の株式投資は100株単位での取引が基本なので、少なくとも数十万円程度の資金が必要になります。
しかし、単元未満株での取引に対応している証券会社を利用すれば、最低1株から購入できるので数百円~数千円で株式投資を始められるのです。
単元未満株投資のメリット・デメリットとしては、以下の点が挙げられます。
| メリット | デメリット |
| 少額で株式投資ができる | リターンが小さい株主優待の対象外になることがある手数料が割高になりやすい |
株式投資は投資の代名詞ともいえますが、ある程度の資金量を求められます。
そのため、株式投資にチャレンジしたい初心者の方は、まずお試しで単元未満株投資から始めてみるのがおすすめです。
初心者にとって簡単とはいえない投資手法は?
これから投資を始める場合、ハイリターン・ハイリスクな投資手法や多額の資金が必要になる投資手法は避けたほうがよいでしょう。
投資難易度が高く、十分な知識・経験がないうちに手を出してしまうと、取り返しのつかない損失を招くおそれがあります。
たとえば、FX・仮想通貨投資・現物不動産投資などは要注意です。
- FX:レバレッジ取引による損失のリスクが大きい
- 仮想通貨投資:値動きが激しく、通貨によっては価値がほぼなくなることもある
- 現物不動産投資:数百万円~数千万円の初期費用が必要になる
また、個別株への投資も経済動向や企業業績などの分析が必要になるため、初心者には難しいかもしれません。
とはいえ、資金量やライフスタイルによって選択すべき投資手法は異なります。
リスク管理を徹底できるのであれば、上記の投資手法を選択肢に入れておくのもよいでしょう。
投資で稼ぐのは簡単?資金別の運用シミュレーション
投資で稼ぐことを具体的にイメージするために、資金別の運用シミュレーションをしてみましょう。
10万円・100万円を元手に、利回り3・5・7%で複利運用した場合における資産の推移は以下のとおりです。
【元手10万円で運用した場合】
| 利回り3% | 利回り5% | 利回り7% | |
| 5年後 | 約12万円 | 約13万円 | 約14万円 |
| 10年後 | 約13万円 | 約16万円 | 約20万円 |
| 15年後 | 約16万円 | 約21万円 | 約28万円 |
| 20年後 | 約18万円 | 約27万円 | 約39万円 |
| 25年後 | 約21万円 | 約34万円 | 約54万円 |
| 30年後 | 約24万円 | 約43万円 | 約76万円 |
【元手100万円で運用した場合】
| 利回り3% | 利回り5% | 利回り7% | |
| 5年後 | 約116万円 | 約128万円 | 約140万円 |
| 10年後 | 約134万円 | 約163万円 | 約197万円 |
| 15年後 | 約156万円 | 約208万円 | 約276万円 |
| 20年後 | 約181万円 | 約265万円 | 約387万円 |
| 25年後 | 約209万円 | 約339万円 | 約543万円 |
| 30年後 | 約243万円 | 約432万円 | 約761万円 |
資産の増え方は元手となる資金量や利回りによって変動しますが、銀行に預けているよりは効率的に資産形成を進められます。
もちろん損失が生じるリスクもあるので、余剰資金を使って投資にチャレンジすることが大切です。
初心者が押さえておくべき投資の基本
初心者の方が投資で利益を出すためには、以下のようなポイントを押さえておく必要があります。
- リターンを求めすぎない
- 「長期・積立・分散」を意識する
- 利益は積極的に再投資する
- 投資アプリで勉強しておく
- ポートフォリオを定期的に更新する
- ロボアドバイザーの利用を検討する
- 公的制度を活用する
いずれも投資の基本といえるポイントなので、正しく理解し、実践で応用できるようにしておきましょう。
リターンを求めすぎない
初心者の方が投資を始める場合は、リターンを求めすぎない姿勢が重要です。
過度な利益追求はリスクを高めるため、安定した資産形成の妨げになります。
たとえば、FXでレバレッジ20倍の取引をすると、一晩で資産の大半を失うことにもなりかねません。
狙うべきリターンは人それぞれ異なりますが、投資経験が浅いうちは利回り3~5%程度を目安にしておくとよいでしょう。
まずは投資を継続させることを意識し、無理のない範囲で取り組むようにしてください。
「長期・積立・分散」を意識する
これから投資を始めるのであれば、「長期・積立・分散」を意識しておきましょう。
「長期・積立・分散」の3原則を徹底することで損失のリスクを抑え、着実な資産成長を実現できます。
| 実践方法 | メリット | |
| 長期投資 | 同じ商品を保有し続ける | 短期的な価格変動の影響を受けずに済むほか、複利効果が発揮されやすい |
| 積立投資 | 定期的に一定額を投資する | 安いときは多めに、高いときは少なめに商品を購入できるので高値掴みを回避できる |
| 分散投資 | 複数の投資対象に資産を分散させる | いずれかの投資先で損失が出ても、ほかの投資先の利益でカバーできる |
利益は積極的に再投資する
効率よく資産を増やしたいのであれば、利益を積極的に再投資していくようにしましょう。
再投資による複利効果を活用すれば、利益が利益を生み出し、資産を雪だるま式に増やしてくことができます。
たとえば、元手1,000万円を利回り5%で運用した場合の資産額をシミュレーションしてみましょう。
元本だけで運用する単利と利益を再投資に回す複利では、資産の増え幅に以下のような違いが現れます。
| 運用年数 | 単利運用 | 複利運用 |
| 1年後 | 10,500,000円(+500,000円) | 10,500,000円(+500,000円) |
| 2年後 | 11,000,000円(+500,000円) | 11,025,000円(+525,000円) |
| 3年後 | 11,500,000円(+500,000円) | 11,576,250円(+576,250円) |
| 4年後 | 12,000,000円(+500,000円) | 12,155,063円(+578,813円) |
| 5年後 | 12,500,000円(+500,000円) | 12,762,816円(+607,753円) |
| 15年後 | 17,500,000円 | 20,789,282円 |
| 30年後 | 25,000,000円 | 43,219,424円 |
元本1,000万円だけを運用し続けても、1年間で得られる利益は50万円のままです。
一方、利益を元本に上乗せしていくと利益はどんどん大きくなり、15年後の総資産は当初の約2倍、30年後には4倍以上にまで膨れ上がります。
投資アプリで勉強しておく
初心者が投資を始める際には、投資アプリで勉強してみるのもおすすめです。
投資を成功させるには実践経験が必要ですが、お金を失うことに抵抗を感じ、知識を取り入れる段階で立ち止まってしまう人も少なくありません。
その点、投資アプリを活用すれば、実際の市場環境を疑似体験しながら投資の基本を学べます。
とはいえ、損失のリスクを背負っているからこそ得られる経験があるのも事実です。
投資アプリである程度経験を積んだあとは、少額からでもいいので、リアルの投資にチャレンジしてみることをおすすめします。
ポートフォリオを定期的に更新する
ポートフォリオを定期的に更新することも、投資の基本といえる作業のひとつです。
時間の経過とともにポートフォリオは崩れていくため、放置していると当初の目標を達成できない可能性があります。
たとえば、保有資産を株式と債券に50:50で配分したとしましょう。
1年後に株式の価値が高まり、資産配分が60:40に変化するとリスク過剰の状態になってしまいます。
そのため、株式の一部を売却したり資金を追加したりして、債券を買い増し、50:50に戻してあげる必要があるのです。
ただし、頻繁にリバランスすると手間も時間もかかるので、「年1回の定期チェック+大きな相場変動時」を目安に取り組むことをおすすめします。
ロボアドバイザーの利用を検討する
初心者が投資を始める場合は、ロボアドバイザーを利用することも検討してみてください。
ロボアドバイザーとは、AIがリスク許容度や目標に応じた最適なポートフォリオを自動構築してくれるサービスです。
プランによっては運用を代行してもらえるので、投資のハードルが一気に下がります。
ただし、ロボアドバイザーへの完全な依存は避けるべきです。
運用方針やリスク許容度の設定は定期的に見直し、AIを使いこなすことを意識しましょう。
公的制度を活用する
投資で効率よく資産を増やしたいのであれば、公的制度を積極的に活用しましょう。
主に「NISA」と「iDeCo」の2種類が挙げられるので、それぞれの制度概要やメリットを詳しく解説します。
NISA(少額投資非課税制度)
NISA(少額投資非課税制度)は、国が認めた非課税制度のひとつです。
通常、投資の運用益には20.315%の税金が課せられるので、100万円の利益が出ても80万円程度しか手元に残りません。
一方、NISA口座での運用益は非課税になるので、100万円をそのまま受け取ることができます。
NISAは1年間に投資できる金額や投資対象などによって「つみたて投資枠」と「成長投資枠」に分類されているので、自身の運用方針に合った制度を選択してください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有期間 | 無期限 | |
| 非課税保有限度額 | 総枠1,800万円(成長投資枠に限っては1,200万円が上限) | |
| 投資対象 | 投資信託 | 株式・投資信託など |
たとえば、投資信託で着実に利益を積み上げたいなら「つみたて投資枠」、株式やREITなどにも投資したいのなら「成長投資枠」がおすすめです。
「つみたて投資枠」と「成長投資枠」は併用もできるので、目的に応じて柔軟に使い分けましょう。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資産の形成を支援するためにつくられた税制優遇制度です。
自身で選んだ商品に毎月定額を投資し、60歳以降になれば元本と運用益を受け取ることができます。
iDeCoを活用するメリットのひとつは、運用益が非課税になることです。
iDeCo口座で運用するだけで約20%の税金を回避できるため、効率よく資産を増やすことができます。
また、iDeCoで拠出した掛金が全額所得控除の対象になる点も大きなメリットです。
拠出した分だけ所得を減らせるので、所得税・住民税の節税効果があります。
ただし、60歳になるまでは原則として資産を引き出せないので、無理のない範囲で積立額を設定するようにしましょう。
投資を始めるのは簡単!基本的な4つのステップ
投資を始める際には、以下のような事前準備が必要です。
- 余剰資金を洗い出す
- 運用目的・リスク許容度を明確にする
- 投資に関する基本的な知識を学ぶ
- 資金量やライフスタイルに合った投資手法を実践する
最初から安定した利益を出せるように、一つひとつのポイントをしっかりと押さえておきましょう。
余剰資金を洗い出す
まずはじめに、余剰資金を洗い出すことが資産形成の第一歩です。
余剰資金とは、日々の生活費や緊急時の備えを差し引いたあとに残る「失っても生活に支障のないお金」のことです。
余剰資金を超えて投資してしまうと、過度なプレッシャーを感じて冷静な投資判断ができなくなります。
その結果、損失が生じた場合には生活苦に陥り、投資どころではなくなってしまうでしょう。
金銭的な余裕がある場合にはじめて、投資が選択に入ってくるのです。
運用目的・リスク許容度を明確にする
投資を始める前には、「運用目的」と「リスク許容度」を明確にしておくことも重要です。
運用目的やリスク許容度によって、選ぶべき投資手法・運用方法は変わってきます。
たとえば、20代独身で旅行代を投資で稼ぎたいのであれば、仮に失敗してもやり直しがきくので、ある程度リスクをとった方法を選択するのも間違いではありません。
一方で、子どもの教育費のために投資を始めるのであれば、できるだけリスクの低い投資手法を選ぶのが適切といえます。
また、投資を続けるうえでは難しい選択を求められるケースもありますが、運用目的とリスク許容度が明確になっていれば、判断に遅れることもないでしょう。
投資に関する基本的な知識を学ぶ
初心者の方は、あらかじめ投資に関する基本的な知識を学んでおくことも重要です。
基礎理解なく始めると、想定外の損失を招いたり、運用益が目標額に届かなかったりする可能性が高くなります。
「長期・積立・分散」の3原則をはじめ、投資の定石といえる考え方は最低限勉強しておくようにしましょう。
ただし、知識を取り入れると同時に、実践でアウトプットしていくことも大切です。
実践経験でしか得られない学びも多いので、机上の学習にとどまり続けることのないようにしてください。
資金量やライフスタイルに合った投資手法を実践する
最後に、資金量とライフスタイルに合った投資手法を選び、実践に移りましょう。
たとえば、十分な余剰資金を確保できない場合には、少額で始められる手法を選ぶのがおすすめです。
仕事や家事が忙しく投資に時間をかけられないのであれば、ほったらかしで運用できる手法を選ぶのがよいでしょう。
手数料がネックですが、ロボアドバイザーを利用してみるのも選択肢のひとつです。
とはいえ、最初から自分に合った投資手法が見つかるとは限らないので、実際に運用しながら、ベストな方法を見極めるようにしてください。
まとめ
これまでお金を銀行にしか預けてこなかった人にとって、投資はハードルの高いものに感じられるかもしれません。
しかし、投資手法は多岐にわたり、それぞれに異なる特徴があります。
少額で始められるものから、事業者に運用を任せられるものまで選択肢は幅広いので、自身の運用方針やライフスタイルにあった手法がきっとみつかるはずです。
そのなかで、簡単な投資手法を探しているのであれば、不動産クラウドファンディングをおすすめします。
不動産クラウドファンディングなら1万円程度で出資できるうえ、投資家はほとんど手をかけずに収益を上げることが可能です。
不動産クラウドファンディングを始める場合は、ぜひ不動産BANKを利用してみてください。
不動産BANKでは、利回り6%以上が狙える魅力的なファンドが随時立ち上がっています。
会員登録もオンラインで簡単に済ませられるので、まずは公式ホームページにアクセスしてみましょう!