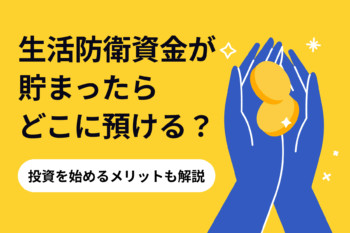近年の日本は、インフレ下にあるといわれています。 給料は変わらないのに物価がどんどん上昇し、生活に余裕がなくなっている人も多いのではないでしょうか。 単に日本円を銀行に預けているだけでは、インフレ時代を生き抜くことはでき […]
近年の日本は、インフレ下にあるといわれています。
給料は変わらないのに物価がどんどん上昇し、生活に余裕がなくなっている人も多いのではないでしょうか。
単に日本円を銀行に預けているだけでは、インフレ時代を生き抜くことはできません。
インフレに強い資産を保有し、将来を見据えた資産運用に着手することが重要です。
そこで本記事では、インフレに強い資産の特徴やおすすめの投資先について解説します。
インフレ対策を成功させるためのコツなども紹介しているので、お金の悩みを少しでも減らしたい方は参考にしてみてください。
- インフレに強い資産の特徴とは?
⇒ 物価上昇とともに資産価値が高まり、長期的にその価値が維持されること - インフレを見据えたおすすめの投資先は?
⇒ 株式・投資信託・不動産・外貨・金などがおすすめ! - インフレ対策の投資を成功させるためのポイントは?
⇒ リスクを抑えて、無理のない範囲で取り組むことが重要!
目次
- インフレに強い資産の特徴
- 特徴①:物価上昇とともに資産価値が上がる
- 特徴②:資産価値が長期的に維持される
- インフレに強い資産・おすすめの投資先6選
- 株式
- 不動産
- 金
- 投資信託
- REIT(不動産投資信託)
- 外貨建ての資産
- インフレ対策するなら不動産クラウドファンディングへの投資もおすすめ
- インフレに強い資産への投資を成功させるコツ
- 余剰資金で投資する
- まずは少額で始める
- 分散投資を意識する
- 長期的な視点で運用を続ける
- リスクとリターンのバランスを調整する
- 公的制度を積極的に活用する
- NISA
- iDeCo
- ポートフォリオを定期的に見直す
- インフレ対策におすすめのポートフォリオ
- インフレ対策の資産運用に関してよくある質問
- インフレに弱い資産は?
- インフレが続くと1,000万円は20年後いくらになる?
- まとめ
インフレに強い資産の特徴
まずは前提となる知識として、インフレとは何か、インフレに強い資産とは何かについて解説します。そもそもインフレとは?
インフレとは物価が持続的に上昇し、お金の実質的な価値が下がる現象のことを指します。
わかりやすい具体例を挙げると、100円で買えていたパンが120円に値上がりしたようなケースです。
これまでと同じように100円を支払ってもパンが買えなくなっており、お金の価値が低下していることを意味します。
実際、近年の日本では著しい物価上昇が続いており、インフレになっているといえるでしょう。
今後もインフレが継続する可能性は十分あるので、早急に対策をとる必要があります。
特徴①:物価上昇とともに資産価値が上がる
インフレに強い資産は、物価上昇に合わせて価値が上がる特徴を持ちます。
たとえば、インフレに強い資産の代表例でもある金の価格は、ここ数年で急上昇し、何度も過去最高値を更新している状況です。
近年のインフレを見越して早い段階から金を保有していた人は、資産が目減りしていないどころか、大きな利益が生じていることでしょう。
ただし、インフレに強い資産だからといって、必ずしも物価上昇と連動するわけではありません。
インフレに強い資産の保有は投資の一環であり、損失のリスクがともなうことを理解しておきましょう。
特徴②:資産価値が長期的に維持される
資産価値が長期的に維持されることも、インフレに強い資産の特徴といえるでしょう。
インフレに強い資産は普遍的な需要があるため、経済環境や市場の変化による影響を受けにくく、時間が経過してもその価値が大きく減少しない傾向にあります。
たとえば、日本のインフレが今後数十年続いた場合、現金の価値は大きく下落するでしょう。
しかし、金・プラチナなどの貴金属や不動産の価値は、現在と同等もしくはそれ以上になっている可能性も十分あるはずです。
ただし、インフレに強い資産といえども、一時的に価値が下落することはあります。
また、資産の種類によっても価値の変動幅には違いがあるので、リスク管理を徹底しておくことが大切です。
インフレに強い資産・おすすめの投資先6選
インフレに強い資産の保有を検討しているなら、以下の投資先がおすすめです。
- 株式
- 不動産
- 金
- 投資信託
- REIT(不動産投資信託)
- 外貨建ての資産
それぞれの資産に異なるメリット・デメリットがあるので、資金量やリスク許容度に応じて選択するようにしましょう。
株式
企業が発行する株式は、インフレに強い資産のひとつといえます。
インフレにともない、企業が製品・サービスの価格をうまく引き上げることができれば、業績が高まり、結果として株価が上昇しやすくなるためです。
特に生活必需品やエネルギー資源などを扱う企業は、インフレ下でも収益を維持できるので、株式の価格も安定しやすい傾向があります。
ただし、株価はさまざまな影響を受けて変動するものです。
災害や従業員による不祥事など予測できない事態によって株価が下落する可能性もあり、常にインフレ対策として機能するとは限りません。
また、すべての銘柄がインフレに強いわけではないため、業種や企業選定を慎重に進めることが成功の鍵です。
不動産
不動産もインフレに強い資産のひとつです。
不動産は実物資産であり、希少性と実用性から価値が下がりにくい特性があります。
場合によっては、物価上昇以上に物件価格が上がり、売却時に大きな利益を得られることもあるでしょう。
また、インフレ時には家賃が上昇する傾向にあるため、定期収入を維持・増加させることも可能です。
さらに、不動産を購入する際にはローンを組むケースが一般的ですが、インフレにより現金の価値が低下すれば、借入額の実質的な負担も減少します。
ただし、不動産を保有するにあたっては、空室リスク・修繕リスク・災害リスクなど、さまざまな損失のリスクを抱えなければなりません。
そのため、需要のある物件を選定し、リスク管理を徹底できる知識・経験が求められます。
金
インフレに強い資産の代表例ともいえるのが金です。
金は世界共通の実物資産であり、供給量が限られているため、その希少性から価格が下がりにくい性質があります。
インフレ時には「安全資産」としての需要が高まり、価格が急上昇するケースも少なくありません。
金に投資する方法としては、以下の選択肢があります。
- 現物の金保有:金塊・金貨・金のジュエリーなどを購入する方法
- 純金積立:毎月一定額で金を購入し、オンライン上で管理する方法
- 金関連の投資信託:金を投資対象に含む銘柄を購入する方法
もちろん、金の価格は常に変動しているため、金投資が損失につながる可能性もゼロではありません。
しかし、長期的な視点でインフレに備えるのであれば、価値が安定しやすい金をポートフォリオのひとつに入れておくことをおすすめします。
投資信託
インフレに強い資産としては、投資信託も挙げられるでしょう。
投資信託とは、不特定多数の投資家から集めた資金を元手に、事業者が資産運用をおこなう金融商品です。
投資信託は複数の投資対象で構成されており、株式・不動産・金などを含む銘柄を購入すればインフレ対策の効果を得られます。
また、「物価連動型」の投資信託はインフレ率を意識した運用がおこなわれるため、インフレ対策としておすすめです。
さらに、投資信託は専門家の市場分析に基づき運用されるので、個人では難しいタイムリーな資産配分により、インフレリスクを最小限に抑えることができます。
ただし、投資信託を保有している間は、運用を事業者に任せるための信託報酬を手数料として支払わなければなりません。
保有額の数%程度ではあるものの、長期運用を前提に考えると資産の増え方が大きく変わってくるため、できるだけ信託報酬率が低い銘柄を選定しましょう。
REIT(不動産投資信託)
インフレに強い資産を保有したいのであれば、REIT(不動産投資信託)に投資してみるのもよいでしょう。
REITは投資家から集めた資金を元手に、事業者が不動産を購入・運用する金融商品のことです。
インフレ時には運用している物件の家賃が引き上げられることも多く、投資家への分配金が増加する可能性は高いと考えられます。
また、REITではオフィスビルや商業施設などの個人では購入できないような物件にも、間接的に投資することが可能です。
そのため、さまざまな選択肢を考慮しながら、インフレ対策ができることも大きなメリットといえるでしょう。
REITには利益の9割を投資家に還元した事業者が税制優遇を受けられる仕組みがあるので、結果的に利回りが高くなりやすい点も魅力のひとつです。
外貨建ての資産
インフレに対する危機感を感じているのであれば、外貨建ての資産を保有するのもひとつの方法です。
物価上昇によって日本円の価値が減少しても、海外の貨幣価値は相対的にみて維持・上昇している可能性があるので、インフレに備えることができます。
具体例として、以下のような外貨建て資産が挙げられるでしょう。
- 外貨預金:米ドルやユーロなどの外貨で預金をおこなう
- 外貨建て投資信託:海外の株式・債券などに投資する銘柄を購入する
- 外国債券:海外の国債や社債に直接投資する
- 外貨建て保険:外貨で運用される生命保険商品に加入する
ただし、外貨建ての資産を保有する場合は、為替変動の影響を直接的に受けてしまうので注意してください。
たとえば、1ドル=100円と1ドル=120円の為替レートでは、ドルから日本円に換金したときに、1ドルあたり20円もの差が生じます。
そのため、日本円もある程度保有したうえで複数の外貨に分散投資するなど、丁寧にリスク管理をおこなうことが大切です。
インフレ対策するなら不動産クラウドファンディングへの投資もおすすめ
インフレ対策としての投資先を探しているのであれば、不動産クラウドファンディングへの投資も検討してみてください。
不動産クラウドファンディングとは、オンライン上で投資家から集めた資金をもとに、事業者が不動産の運用をおこない、収益を分配する仕組みのことです。
インフレ時には不動産の物件価格や家賃が上昇する傾向にあるため、結果的に不動産クラウドファンディングを通じて得られる分配金も安定する可能性が高いと考えられます。
また、不動産クラウドファンディングは1万円程度の少額から始められるので、初心者の方にもおすすめです。
不動産クラウドファンディングサービスに興味がある方は、ぜひ不動産BANKの公式サイトをチェックしてみてください。
不動産BANKでは、資産価値が落ちにくい首都圏の中古物件を中心に取り扱い、年利6%の高利回りを安定的に達成しています。
魅力的なファンドが随時立ち上がっているので、まずは一度、試しに応募してみましょう!
インフレに強い資産への投資を成功させるコツ
インフレに強い資産への投資を始めるのであれば、以下の7点を意識しておくとよいでしょう。
- 余剰資金で投資する
- まずは少額で始める
- 分散投資を意識する
- 長期的な視点で運用を続ける
- リスクとリターンのバランスを調整する
- 公的制度を積極的に活用する
- ポートフォリオを定期的に見直す
いずれも投資の基本ともいえるポイントばかりなので、一つひとつ詳しく解説します。
余剰資金で投資する
インフレに強い資産への投資を成功させるには、余剰資金を用いることが重要です。
余剰資金とは、日々の生活費や緊急時の備え、近い将来使う予定のあるお金を差し引いたあとに残る資金のことを指します。
余剰資金を超えて投資していると、損失に対する恐怖・不安の感情が過度に生じてしまい、冷静な投資判断ができなくなってしまうのです。
インフレへの備えも大切ですが、まずは当面の生活を最優先に考えるようにしてください。
まずは少額で始める
インフレに強い資産への投資は、少額で始めることをおすすめします。
投資初心者の方は損失を出してしまうことも多いですが、そもそもの投資額が小さければ、損失のダメージもそこまで大きくならないはずです。
そのため、リスクを抑えながら投資経験を積み、長期的な資産形成の基礎を築くうえで、少額投資は最適な方法といえます。
金や不動産などの高価な資産も、投資信託やREITを活用すれば少額の資金で保有することが可能です。
いずれ投資に慣れてくれば、投資額を増やして、インフレ対策を手厚くしていくのもよいでしょう。
分散投資を意識する
インフレに強い資産への投資を始める際には、分散投資を意識しましょう。
インフレ時の値動きは、資産の種類によって異なります。
そのため、複数の資産に分散投資しておけば、いずれかの投資先で損失が生じた場合でも、ほかの資産の利益でカバーできる可能性があるのです。
なお、分散投資の効果を高めるには、値動きの異なる資産をうまく組み合わせる必要があります。
ポートフォリオの作成に自信がない場合は、インフレに強い複数の資産で構成された投資信託の銘柄をひとつ購入することから始めてみてください。
長期的な視点で運用を続ける
長期的な視点で運用を続けることも、インフレに強い資産への投資を成功させるためのポイントです。
インフレに強い資産は物価上昇とともに価格が上がる傾向にありますが、短期的には激しく価格が変動することも珍しくありません。
そのなかで目先の利益を追いかけようとすると、一時的な価格変動に惑わされ、合理性に欠けた投資判断をしてしまいます。
物価は基本的に少しずつ上昇していくものなので、インフレ対策としての資産運用も長期的な視点でおこなうようにしましょう。
また、投資信託やREITのように定期的に分配金が付与される金融商品であれば、利益を再投資に回し、長期的に運用することで、複利効果が発揮されやすくなります。
リスクとリターンのバランスを調整する
インフレに強い資産に投資する際は、リスクとリターンのバランスを調整する必要があります。
投資の世界において、リスクとリターンは比例関係にあるものです。
ハイリターンを求めると、その分リスクが高まり、取り返しのつかない損失を生み出してしまう可能性も否定できません。
一方で、リスクを徹底的に廃除すると思うようなリターンを得られず、インフレ対策としては不十分な結果に終わってしまうでしょう。
そのため、まずはそれぞれの投資先がもつリスク・リターンの比重を理解し、うまく組み合わせてバランスをとることが大切です。
公的制度を積極的に活用する
インフレに強い資産に投資する際は、公的制度を積極的に活用しましょう。
公的制度を活用すれば税制面で優遇されるため、効率的に資産運用を進められます。
主にNISAとiDeCoの2種類があるので、それぞれの制度概要やメリットを詳しく解説します。
NISA
NISAは、少額での投資を支援するために作られた非課税制度です。
日本国内に住む18歳以上であれば、基本的に誰でもNISA口座を開設することができます。
NISA口座で投資するメリットは、運用益が非課税になることです。
通常、投資の運用益には20.315%の税金が課せられるため、100万円の利益が出ても手元には80万円程度しか残りません。
一方、NISA口座を使えば、税金が差し引かれないので100万円をそのまま受け取れます。
なお、NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2種類があり、年間で投資できる金額や投資対象の範囲に違いがあるので、自身に合ったほうを選んでください。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有期間 | 無期限 | |
| 非課税保有限度額 | 総枠1,800万円(成長投資枠に限っては1,200万円が上限) | |
| 投資対象 | 投資信託 | 株式・投資信託など |
たとえば、長期的なインフレ対策として投資信託を保有するつもりなら、つみたて投資枠がおすすめです。
一方、株式やREITもポートフォリオに含めたいのであれば、成長投資枠を選択するのがよいでしょう。
とはいえ、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」は併用も可能なので、柔軟に運用を進められるはずです。
iDeCo
iDeCoは、老後資産の形成を後押しするために作られた個人型確定拠出年金のことを指します。
基本的に20歳以上65歳未満の公的年金被保険者であれば、iDeCoに加入することが可能です。
iDeCoの加入者は、自分自身で決めた投資対象に毎月一定額を拠出し、資産運用をおこなうことになります。
iDeCoに加入するメリットは、NISAと同様に運用益が非課税になる点です。
20.315%の税金を差し引かれることなく、運用益をそのまま受け取れるので、効率よく資産形成を進められます。
また、掛金が全額所得控除される点もiDeCoを利用するメリットのひとつです。
たとえば、年収500万円の会社員が毎月2万円を拠出した場合は、所得税・住民税がそれぞれ2万4,000円ずつの計4万8,000円を節税できます。
ただし、iDeCoで運用している資産は、原則60歳になるまで引き出すことはできません。
iDeCoが原因で生活が圧迫されることのないように、無理のない範囲で掛金を設定するようにしましょう。
ポートフォリオを定期的に見直す
インフレに強い資産への投資をおこなう際は、ポートフォリオを定期的に見直すようにしましょう。
インフレによる影響や経済情勢の変化などにより、保有している資産の価値は変動していきます。
そのため、放置したままにしていると資産配分が当初の計画からズレて、リスクが偏る可能性があるのです。
たとえば、株式と金を50:50で購入した半年後に金の価格が上昇し、資産配分が40:60に変化した場合は、金を売却して株式を購入するか、資金を追加して株式を買い増しする必要があります。
ポートフォリオを見直す頻度は、年に1~2回が目安です。
定期的な見直しを習慣化すれば、インフレに強いポートフォリオを維持し、長期的な資産形成を成功させることが可能になります。
インフレ対策におすすめのポートフォリオ
ここでは、インフレ対策におすすめのポートフォリオを3つ紹介します。
とはいえ、最適なポートフォリオは人それぞれ異なるので、あくまでも参考程度に捉えるようにしてください。
| テーマ | 資産配分 | ポイント |
| 実物資産重視型 | ・金(35%)・REIT(35%)・穀物関連ETF(30%) | ・金や穀物を対象にしたETFはインフレ時に価格が上昇しやすく、REITは賃料収入を通じた安定収益が期待できる・金やコモディティの価格は短期的に大きく変動することも多い点に注意が必要 |
| グローバル分散型 | ・米国株式ETF(40%)・外国REIT(30%)・エネルギー関連株式(20%)・金ETF(10%) | ・米国株式と外国REITで地域分散を図り、エネルギー関連株式でインフレ時の価格上昇を狙う・金ETFはインフレ時の安全資産として機能・為替リスクをともなう点に注意が必要 |
| 成長型ポートフォリオ | ・国内成長株式(50%)・海外成長株式(30%)・金積立(10%)・不動産クラウドファンディング(10%) | ・株式中心で高いリターンを追求しつつ、金積立と不動産クラウドファンディングでインフレのリスクヘッジ・株式市場の変動リスクが大きいので、株式の割合は個別の調整が必要 |
いずれのポートフォリオも定期的な見直しと調整をおこなうことで、インフレ対策としての効果を最大化できます。
インフレ対策の資産運用に関してよくある質問
最後に、インフレ対策の資産運用に関してよくある質問を紹介します。
余計な心配をせずにインフレ対策を進められるよう、疑問は早めに解決しておくことが大切です。
インフレに弱い資産は?
インフレに弱い資産とは、物価上昇にともない実質的な価値が目減りしやすい資産を指します。
具体的には、現金や固定金利の預金、一部の保険商品などが挙げられるでしょう。
まず、現金は物価が上昇しても額面が変わらないため、同じ金額を保有していても資産の価値としては下落していく一方です。
固定金利の預金も、超低金利下ではインフレ率に追いつけず、実質的な資産価値の減少は避けられません。
同様に、契約時に固定された金額を受け取れる保険商品も、インフレ進行により受取金の実質的な価値が下がってしまうリスクがあります。
上記の資産にもそれぞれメリットがあるためポートフォリオに入れておくのもよいですが、インフレに強い資産への移行も同時に検討することが重要です。
インフレが続くと1,000万円は20年後いくらになる?
2024年の消費者物価は、2~3%上昇していました。
このまま年3%の物価上昇が20年間続くと仮定すると、現在の1,000万円は約550万円まで価値が目減りする計算です。
もちろん、今後の動向は正確に予想できませんが、近年において物価が上昇傾向にあることは確かなので、早急に対策しておく必要があります。
まとめ
著しい物価上昇が続くなか、インフレ対策は必要不可欠です。
大切な資産を守るためにも、無理のない範囲で、インフレに強い資産の保有を検討してみてください。
インフレに強い資産には株式・不動産・金などが挙げられますが、人によっては資金不足で手が届かないこともあるかもしれません。
そこで、少額からインフレ対策を始める方法として、不動産クラウドファンディングをおすすめします。
不動産クラウドファンディングであれば、1万円程度からでも出資可能です。
また、不動産を投資対象としているので、インフレ対策の効果も期待できます。
不動産クラウドファンディングを始めてみたい方は、ぜひ不動産BANKを利用してみてください。
不動産BANKでは、高利回りを狙えるファンドが随時立ち上がっています。
ファンドへの出資に必要な手続きはすべてオンラインで手軽に進められるので、まずは会員登録だけでも済ませてみてはいかがでしょうか。